未来のアーティストたちが眠る部屋を作るのは誰か? 国立西洋美術館「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展レビュー(評:半田颯哉)
会場風景より、弓指寛治の展示
目を醒まさせた抗議活動
美術館内での抗議活動が話題となった、国立西洋美術館の「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? —— 国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」展。もしこの抗議がなければ、正直に言うとこの展示に対して期待の気持ちはなく、それどころか足を運ぶか否かすら悩んでいた。
それはこの展示の枠組みに疑問を抱いていたからだ。日本の国立美術館なのに、「西洋」に特化しているという矛盾。しかし、そのハイレベルな収蔵品と、明治維新以降に醸成された日本人の西洋文化への憧れによって、国内トップレベルの来場者数を持つひとつの権威的な美術機関であり続けている。基本的に物故作家のオールドマスターしか扱ってこなかった国立の権威が、現代アーティスト、それもほとんどが日本出身で存命の作家を扱うというのは、確かに大きなブレイクスルーだろう。
いっぽうで、「自館のこれまでの枠組みを問う」という美術館・博物館の取り組みは、決して珍しいものではない。たとえば、多くの国の美術館で「脱植民地主義」は重要なキーワードのひとつとなっており、加害的な業績を持つ人物を描写した作品に注釈を追加したり、展示全体のキュレーションとしてマイノリティの視点からのナラティブを提示するなどの試みが起きている(*1)(*2)。日本においても、小企画展「男性彫刻」を開催し、ジェンダーの観点で所蔵品の見直しを推し進めている東京国立近代美術館、女性作家の作品やアボリジナル・アートのコレクション拡充を進めているアーティゾン美術館などで、展示や館全体の方針見直しが進められている。あるいは広島市現代美術館の開館30周年記念特別展として開催された「美術館の七燈」展、および「リニューアルオープン記念特別展 Before/After」展は、「美術館の機能とは何か」、そして「広島の現代美術館の役割とは何か」という問いに館として向き合い、まさに「自館の枠組みを改めて見詰め直す」取り組みであった。
各地の美術館・博物館でこうした見直しが進みつつあるなかで、「自館のこれまでの枠組みを問う」だけでは、その取り組みをクリティカルなものだと評価することはもはや難しいだろう。そして、いまや「どのように枠組みを問い直すのか」という視点の深さや独自性こそが問われるべきフェーズへと移行するべきだ。

本展の開催発表に際して目にした参加アーティストの一覧は、このような目線で見たときに踏み込んだ企画だとは感じられないラインナップだった。たとえば、飯山由貴、遠藤麻衣、鷹野隆大、長島有里枝、ミヤギフトシの名前の並びからは、ジェンダーの視点が期待される。梅津庸一、杉戸洋、辰野登恵子、松浦寿夫をつないだ線からは、絵画という媒体への信念が見える。小沢剛、小田原のどか、田中功起からは制度への問い直しが、ユアサエボシ、弓指寛治からは物語と絵画の関係性が……といった具合に、参加アーティストの一部をつなぐことで複数の線を引くことができる。しかし、その全体をつなごうと思ったとき、「日本を拠点とする現代アーティスト」以外の線を見出すことができないのだ。
「西洋美術館で現代アートを扱った」。その点しか着目するべきことが見つからず、展示へ足を運ぶモチベーションがほとんど持てないでいたなかで、飯山由貴らによる抗議活動は「予定調和」的な雰囲気に風穴を開け、私の目を醒まさせた(*3)。しかもそれは、「美術的」にパレスチナを消費するのではなく、市民としてデモを持ち込んだことの真摯さを感じさせるものであった。そして会場で配布されたビラに記された内容は、西洋美術館の成り立ち——抗議対象の川崎重工業の前身である川崎造船所とその初代社長だった松方幸次郎が、イギリスのプロパガンダポスターに感銘を受けて松方コレクションを始めたとされている——に絡めたものだった。まさに、西洋美術館の在り方への脱植民地主義的な掘り下げであり、一転、私はこの展示に強く興味を惹かれたのだ。そんなわけで早速、展示が始まって最初の日曜日に上野へと足を運んだ。
展示を見終えたあと真っ先に口をついた感想は「疲れた」だ。SNS上でも「4時間かかった」という投稿を見かけ、前情報として見終わるのに時間のかかる展示だとは認識していたが、実際に私も3時間半かかった。その要因のひとつはとにかくテキストが多いことにある。展示の章立てや各作家・作品の紹介文のみについて言えば特段多いというわけではない。しかし、各作家の用意したテキストがとにかく多いのだ。普段から批評や出版などを通して文章を発表する作家が多く選ばれていることがその一因だと思うが、もしかするとそれは、自身がどのような活動をしているのかを自ら説明していく文章が無ければ、現代アーティストは西洋美術館とは接点を持つことが難しいということなのかもしれない。
日本社会に実装すべき提言を行った田中功起
だがそうした疲労はありつつも、非常にいい作品/取り組みに向き合うことができ、展示の「読後感」はいいもので、とくに田中功起と弓指寛治が見せた取り組みには胸を打たれた。

田中は作品でなく、美術館側に6つの提言を出し、また文化研究者・山本浩貴に依頼した自身の提言への批判と合わせてそれを掲示した。
【田中による美術館へのプロポーザル】
美術館へのプロポーザル1:作品を展示する位置を車椅子/子ども目線にする
美術館へのプロポーザル2:乳幼児向けの託児室を設ける
美術館へのプロポーザル3:河原温の『純粋意識』に倣ったキッズスペースを設ける
美術館へのプロポーザル4:展示台や椅子などの什器製作を誰に頼むのか
美術館へのプロポーザル5:公共施設での翻訳言語の選択を拡張する
美術館へのプロポーザル6:観客として想定されている『市民』を疑う
田中の提言は美術館の公共性を問うものであり、その公共性とは山本が指摘するように「『みんな』から排除されがちな社会的な弱者にしっかりと目を向けること」(*4)だ。田中は自身の子供が産まれて以降、子供に向けた美術についても考えるようになったと話していたように思う(*5)。本展での田中の取り組みで子供に関する言及が多いのは田中の育児の実体験に基づいていることが伺えつつも、同時に日本社会の構成員のひとりとして美術館の「公共性」に誠実に向き合おうとしていることがわかる。「美術館へのプロポーザル5:公共施設での翻訳言語の選択を拡張する」において田中は翻訳言語に英語、韓国語、中国語だけでなく、トルコ語、クルド語を加えることを求めた。昨今、クルド人移民に対して、日本では急速に排外主義の新たな矛先が向けられるようになりつつある。そのようないままさに眼前で起きている公共からの排除、あるいは「我々に合わせろ」という同化の要求に対して、まずは彼らの言語を「公共」に内包しようとするための田中のアクションであると受け取った。また「美術館へのプロポーザル1:作品を展示する位置を車椅子/子ども目線にする」は、本展の中の田中の割り当てられた展示スペースのみならず、西洋美術館のコレクション展においてもいくつかの作品において実施されていた。これまでマイノリティ側にのみ課せられていた「不便を受け入れる」ことを転換していくための取り組みの第一歩だっただろう。
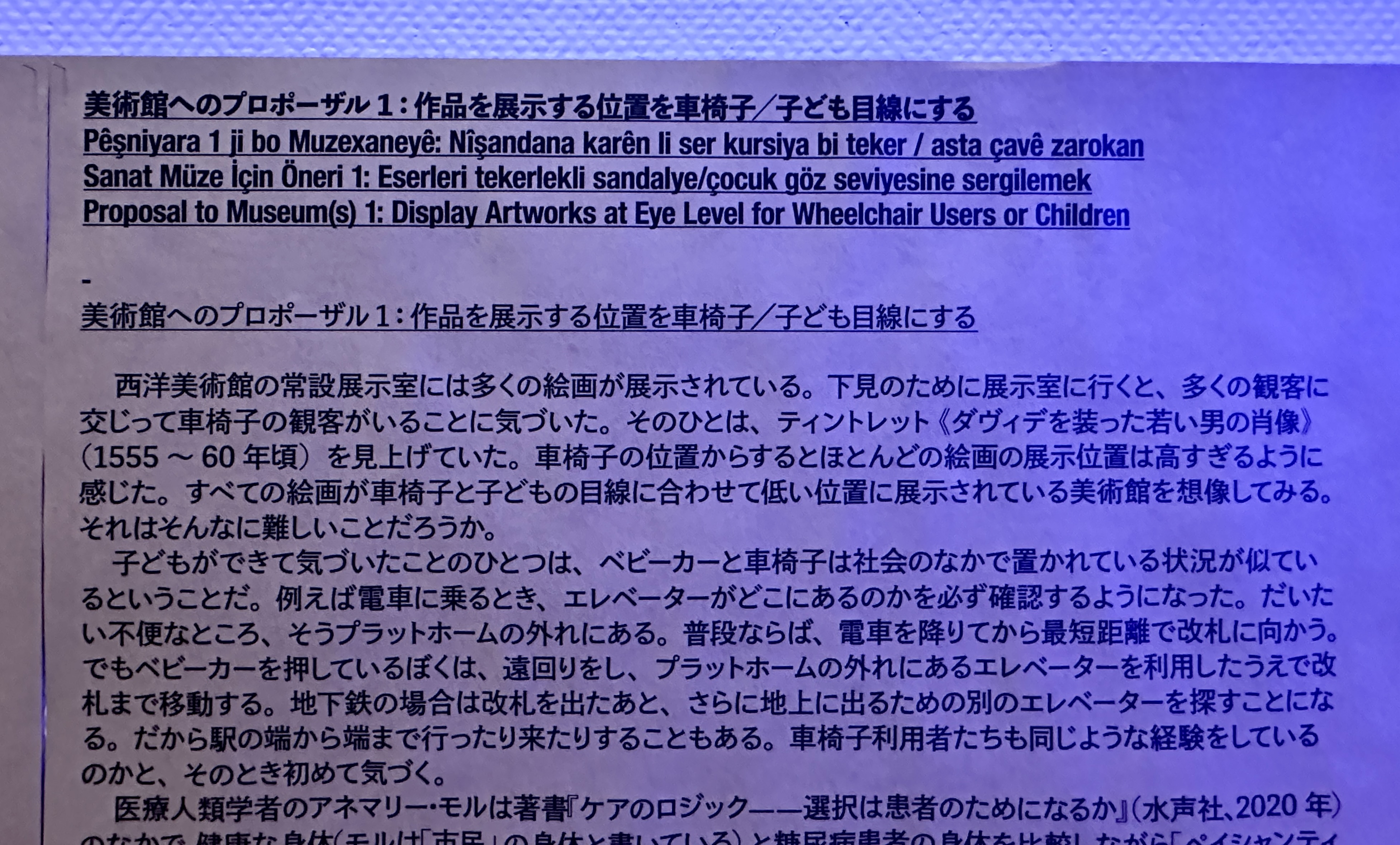
田中が美術館側に提示し、いくつかは実行に移されたこの提言は、アートというよりもデザインの領域にあるものだと思う。そしてそこにこそに田中の真摯さがあるのではないだろうか。田中が美術館の中に見出した「非公共性」を机上の理想としてのアートにするのでもなく、また西洋美術館をお題にした大喜利のような取り組みに落とし込むのでもなく、ただただいまの日本社会の中に入れ込むべき、実効性のあるユニバーサルデザインの提言・実装が志されていた。作品に責任を持つアーティストとしての枠を踏み出した、日本社会の、そして日本の美術館制度の構成員のひとりとして美術館の枠組みに向き合った結果のアウトプットだった。
ホームレスの人々に向き合った弓指寛治
弓指寛治の作品はかつて上野公園に多くいたホームレスの人たちの現況や人生をリサーチしていくものだ。そのきっかけは本展を企画したキュレーターの新藤淳からの打診で、弓指が会場に掲示したテキストによれば、新藤は上野公園内にある西洋美術館に長年いるにもかかわらず、ホームレスの人たちを見て見ぬふりをしてきた自覚があるという。
弓指も打診を受けるまでとくにホームレスの人たちとの接点もなく興味もなかったというが、まずは自身の周囲に「ホームレスの知り合いはいるか?」と尋ねるところからリサーチを始め、ホームレスという概念からその人々への実態へ、そしてあるホームレス個人の物語へと解像度を高めていく。
展示順路に並ぶ弓指の言葉と絵画作品によって、鑑賞者は絵本を捲るように弓指のリサーチを追体験することができる。弓指が昨年の奥能登芸術祭で見せた作品も、ある飛行機少年が日本兵となり歩んだ戦中・戦後を、険しい山道を歩きながら追いかけていくものだったが、今作でもやはり鑑賞者の歩みと物語の進行を巧みに結びつけている。
特筆すべきはそのテキストで、「読ませる」うまさがあるだけでなく取り組みへの真摯さが伝わってくる。弓指の作品はその状況のみを記述すれば、「ホームレスの経験もなければ興味を持ったこともなかった"現代アーティスト"が突然やってきて調査を行い、作品の材料にする」というものだが、しかし、あるいはだからこそ、弓指の言葉はどこまでも等身大なものとなっている。ホームレスの人々の実態について上から目線で決めつけることなく、突然どこかに一足跳びで来訪するのでもなく、まず自身の周りに尋ねるところからリサーチを始め、そして自身でホームレスの人と、またその支援者たちとコミュニケーションを取っていく。もちろん、弓指が「他者」を語ることの問題は依然としてそこに残り得るが、私は「自身の視点で他者を語る」ことを丁寧に引き受けた作品だったと思う。
展示の終盤では、それまでのテキストの多い作品群とは打って変わって、第6章のパープルーム、ユアサエボシを嚆矢として引き継ぎつつ、第7章が非常にシンプルに現代作家と西洋美術館のコレクション作品が対置された、絵画作品(と梅津庸一の陶芸作品)を楽しむ空間となっていた。ここまでテキストの読解と作品の解釈をし続けて疲れていたところだったので、視覚的な快に身を任せることのできるこの空間には解放感があった。また本章の展示テキストは非常に明快であり、おそらくキュレーターが得意とする絵画分野の分析の手腕が遺憾無く発揮されているのだろうと感じられた。第7章の解放感と、田中、弓指の両名による作品の余韻が、この展示の「いい読後感」につながっていた。


展示に感じた物足りなさ
しかしこの「いい読後感」は一部の作品によるものであるという感覚も確かにあり、掘り下げが浅く感じられる作品もあった(ここに挙げる作品は例示であり、これらが取り立ててよくなかったということではない)。
たとえば、鷹野隆大はIKEAの家具を配置した「部屋の中」に西洋美術館の所蔵品と自身の作品を併置していた。規格化された生活家具の中に非量産品の最たるものである美術品を並べるという脱構築性、また西洋美術館の所有する「権威的な」西洋絵画を生活空間という権威性とは正反対な場所に配置するという脱権威性が提示されたのはよくわかる。また、オールドマスターの西洋絵画に描かれている「まなざしを向けられるジェンダー像」を照射し、自作の対置によってそれを際立たせようとする意図も理解できる。しかし、そうした操作はいずれもシンプルかつ既視感のある試みであり、重層的な読解を喚起されることはできなかった。
小田原のどかは、自身の論考と転倒させたオーギュスト・ロダンの《青銅時代》《考える人》、西光万吉の掛軸、西洋美術館の開発した免震台、松島の五輪塔を模した赤い塔と座椅子を展示した。横倒しになったロダンの彫刻は、鑑賞者が下から眺めることが可能となっており、その鋳物の中を覗き込むことのできる貴重な機会となっている。小田原は壁に掲示した論考で、彫刻を横倒しにしたことを関東大震災で被災したロダンの作品になぞらえているとしている。そしてその転倒を、BLM運動のなかで倒された奴隷商の立像や、東アジア反日武装戦線によって爆破された《風雪の群像》、さらには水平社宣言を起草した西光万吉のその後の思想転向と重ね合わせていく。

しかし、かつて地震で倒れたロダン作品があったから西洋美術館でもロダンの作品を転倒させる、というのは少々安易に感じられる。また、《風雪の群像》から派生して、小田原はアイヌの人々の住む北海道への日本の入植と、アメリカ、イスラエルによる入植へも言及を広げていくが、地震という天災による彫刻の被災と、反差別運動のなかで行われた彫刻へのアクション、加えてそこに人権運動家の思想の転向を並列して並べるというのは、(いかに小田原自身もそれらを「同列視することはでき」ないとその論考で述べていたとしても)あまりにそれぞれの立脚する文脈が異なり、「それらの差異を個別具体的に論ずること」は困難なように思う。小田原の論考のうち、第6章のトピックは「彫刻から『わたしたち』を問う」ことにあった。しかしむしろ、本作においては小田原自身がひとりの日本出身のアーティストとして、彫刻の置かれたどのような状況について述べたいのか、それをどのような「わたし」として述べているのかを問い直して欲しかった。
もちろん、所在不明だった西光の自画像《毀釈》を見つけ出しただけでなく、日本において初めてロダン彫刻の修復を行った高村豊周の随筆を論考で引用し提示するなど、本作における小田原のリサーチには感嘆させられた。また、ロダンの彫刻を内側から見た豊周視点からその構造的強さを技法的に示していたのは、やはりロダンの彫刻を下側から覗き込むこととなった鑑賞者の解像度も上げることにつながっていた。アーティゾン美術館での「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」展は、山口の画家としての視点を存分に発揮してその制作プロセスをリバースエンジニアリングするような展示であり、アーティゾン美術館の収蔵する平面作品の見方を拡張していくような解説となっていたが、せっかくのロダンの彫刻の構造が垣間見えるこの作品において、彫刻家である小田原の制作者としての目線が向けられたものとなっていたならば、それはまた違った視点と魅力を鑑賞者に与えてくれる作品となっていたのではないだろうか。
飯山由貴の作品においては、田中功起の提言を見た直後だったこともあり、まずアクセシビリティの問題が気になってしまった。飯山は黄色ベースの壁紙が貼られた壁面に、松方コレクション・旧松方コレクションの作品を掛け、その成り立ちを起点とした手書きテキストを提示していた。

まず、このテキストが非常に読みづらい。手書きのテキストはそれ自体が読みやすさを減じてしまうが、加えて文字が小さく、高さのある壁面を見上げたときに上の方の文字の視認が難しく、配置されている絵画作品の額縁が邪魔になり物理的に視界が遮られてしまうことも起きていた。日本人男性の平均身長ほどの背丈がある私でもそのような見づらさが感じられたので、背の低い鑑賞者や、それこそ車椅子ユーザーの鑑賞者にとってはさらに見づらい作品だっただろう。また日本語の手書き文字は日本語を母語としない鑑賞者に対して高いハードルを課してしまうのではないだろうか。あるいは、壁面のテキストにあるようにこれは「作り手が私自身の物語をつくること」の試みだったかもしれないが、他者に伝わるものとならなければ、その物語は力を持たないか、自身とその協力者のなかで強い力を持つのみで完結する物語となってしまう。
テキストの内容自体も、松方コレクションの成り立ちがプロパガンダ美術のためにあったのではないかとされていることから始まるものの、それが深められていくのではなく、そこから国立近代美術館が管理する戦争画、日本の植民地主義、ジェンダー間の不均衡な権力についてと内容が発散してしまっていた。まさにプロパガンダで行われるような、強者が物語を作っていくことの暴力性を軸とし語りを展開させていっているのはわかるが、やはりどうしても並列的に見え、ソリッドな批判性を持つことはできていなかった。
飯山はこのほかに、右側の壁面に設置された紙と鉛筆で鑑賞者に参加を促す作品も展示していた。鑑賞者に対して壁面に書かれた問いは、「あなたの心や体を支配するものやひとはなんですか? それをかいてください。言葉でも絵でもかまいません。」「あなたを支配するものやひとについて、なにか言いたいこと、伝えたいこと、怒りたいことがあったらそれをかいてください。言葉でも絵でもかまいません。」だった。こうした参加型の作品は飯山が継続的に取り組んでいるのものだと思うが、やはりよく見る手法であるというだけでなく、このパブリックな場で書ける範囲の内容を掲示し共有することに、実行的な「自身の物語をつくること」の力を見出すことはできなかった。また私が来訪したタイミングでは用紙のストックがなく、ここでも鑑賞体験のデザインの部分が気になってしまった。
キュレーターシップはそこにあったか?
前述した通り、この展示の「読後感」は決して悪いものではなかったが、それは田中の取り組みと弓指の作品に心動かされ、また最終章で絵画空間に浸ったことでテキストからの開放感も得られたからだろう。そして展示の評価はそうした一部の作品や最終章のカタルシスによってのみ行うのではなく、また個別の作品の良し悪しを語ることに依るのでもなく、それらとは独立して行う必要がある。展示全体を通して見ると、やはり事前に展示の概要から感じていた通り、「日本を拠点とする現代アーティスト」以外の線を見出すことができなかった。「西洋美術館で現代アートをやる」以外のキュレーターの視点がなく、キュレーターシップが欠如しているように感じられたのである。
たとえば鷹野の作品は、この展示のなかにあっては掘り下げの弱い作品と見えてしまっていたが、もしこれがジェンダーに焦点を当てた展示の一部を構成していたならば、ここからよりクリティカルな内容に進んでいくための導入であったり、視点を多様化するためのピースのひとつとなっていたかもしれない。あるいは、西洋美術館の所蔵品に対する現代作家の視覚的な呼応が主題となっていた、第1章、第6章、第7章の内容に絞って展示が行われていたのであれば、この展示での着眼点のはっきりした、まとまりのある展示となっていただろう。それぞれトピックの大きく異なる7章立ての展示というのはあまりにも区分が多く、その章同士も相互につながりを持つものとはなっていなかったがために、展示全体の流れがそれぞれの作品を活かすものでなく、孤立させ、持ち得た魅力を引き出すことのできないものとなってしまったのではないだろうか。こうした展示の断続性は、テキストの多さとも無関係でなかっただろう。展示を十全に享受しようとすると、鑑賞者は一つひとつのテキストに没入することを求められ、作品同士の有機的なつながりをより困難にしてしまう。
キュレーターシップとは、いかにして展示の責任をキュレーターが負うかということでもあると言える。それは、どのような作家・作品を選出するか、あるいはしないかということでもあるし、どのように展示にまとまりを持たせ、また意外性を加えるかということでもあるだろう。しかしそうした展示の内容以上に、キュレーターの「責任感」が欠如していたように感じられるポイントもあった。
まず、せっかくの田中による提言が限られた範囲でしか適用されていなかったという部分だ。たとえば、コレクション展において、「美術館へのプロポーザル1:作品を展示する位置を車椅子/子ども目線にする」を適用することができた作品は一部のみだったが、館のマネジメントとして全作に適用することは難しかったのはわかる。しかし、本展において田中の提言が適用されていたのが田中のパートと展示の挨拶文のみだったのは非常に残念なポイントである。個別の作家の作品内への介入は難しいにしても、せめて章ごとのテキストにおいては田中の試みに呼応することはできたのではないか。キュレーターがそこに応えられなかったことは残念に思えた(*6)。
そしてもっとも気になったのは、弓指の作品から垣間見えるキュレーター・新藤のスタンスである。新藤は自身の気にかけていたホームレスの人々の存在のリサーチを弓指に投げかけるが、なぜそれを新藤自身が手がけなかったのだろうか。あるいは、新藤自身がホームレスのみにフォーカスせずとも、あるときは男娼の森と呼ばれ、あるときは在日イラン人の交友の場となっていた上野公園という場所の持つ、不可視化に追いやられてきた人々の歴史に目を向ける展示を組むこともできただろう。結局のところ、ある種の安全圏から自身の視点を提示せずに現代美術の上澄だけを集めた本展の姿勢は、弓指が見せた等身大の姿勢とは対極に位置するように思える。
西洋美術館へ入館した瞬間、「現代美術の展示はこちらです」と案内の声をかけられた。この場所、西洋美術館においては、現代美術はまだ展示タイトルや内容ではなく、「非西洋前近代・近代美術」としてしか認識されていないということを思い知らされる言葉であった。ゆえにこの展示が西洋美術館にとっては革新的だったことも、またその観客に新たな出会いをもたらしていたこともわかる。そうした美術館で現代美術を取り扱おうとするキュレーターは調整に追われる毎日だったかもしれないし、そのなかでなんとか通せた企画が通り一遍の現代美術を提示するというものだったのかもしれない。しかし、「西洋美術館で現代美術を扱う」というような一元的な革新性で良しとしていては、美術館が未来のアーティストの眠る場所たりえることはないだろう。この展示で必要だったのはまさに自問であり、その問いかけは「現代美術家たちへ」ではなく、「キュレーターへ」と向けられるべきであり、キュレーターたちこそが「未来のアーティストたちが眠る部屋」を作っていかなければ、そこに未来のアーティストたちが眠ることはないだろう。
*1──キュレーター・八巻香澄がオランダ滞在の経験を起点に書いたレポートは、近年のヨーロッパにおける博物館の「脱植民地主義」について理解するための日本語資料として参考になる。 https://artscape.jp/focus/10182871_1635.html
*2── NHKでもこの4月に「ミュージアムの脱植民地化」と題した『視点・論点』の回があった https://www.nhk.jp/p/ts/Y5P47Z7YVW/episode/te/477YGNWRNG/#article
*3──内覧会の「騒動」について、註釈として筆者の考えを残しておきたい。まず、筆者のスタンスを明らかにしておくと、飯山の内覧会における抗議行動については賛意を示す立場だ。だが、それについての議論もまた否定すべきものではなく、抗議活動はどれくらい有効なのか、あるいはこれを抗議活動として見るべきなのか、美術として評価すべきなのか、美術という枠組みに収めるべきではないのか、美術館はどういう場としてくべきなのかなど、ある単一的な論点を絶対的な定規とすることなく複合的な質的議論を交わし、またそのどれを重要なものとしていくかを擦り合わせていくべきだろう。ただそのうえで、現段階でわかっている情報からの判断になるが、そうした議論を超えた日本の表現の自由に関する憂慮がある。美術館側からの通報があったわけでもなく、また展示の内覧会に入れる人間は限られているにもかかわらず、部外者たる私服警官が美術館内に入ることができ、デモの様子を撮影し、ビラ配りを止めようとしたというのは警察による一線を超えた介入だったのではないだろうか。
*4──展示掲示文・山本浩貴「田中さんのステートメントを読んで」《[補遺]アーティストへのプロポーザル1:自分自身の立ち位置を疑う》より。
*5──筆者は田中の講演「過去を編集する/方法としてのレトロスペクティブ」(2022年6月20日 https://repre.c.u-tokyo.ac.jp/2022/06/06/田中功起氏講演会/ )にてその旨の発言を耳にしたと記憶している。
*6──より大きな視点では、キュレーターを擁する美術館側の問題もある。Seina Morisakoが「日本の美術館においてベビーカーが透明でなくなる転換点に居合わせた透明だったかつての私。」( https://note.com/seina/n/n042b3edad8cc )で指摘するような、強い立場にある男性の指摘によってやっと物事が動くという問題も美術館サイドの責任の問題ではないだろうか。私としては「強い立場にある男性」として声を挙げた田中を支持しつつ、これまで問題として取り上げることのできなかった美術館の方にやはり批判の目を向けたい。
※追記:本レビュー公開後、小田原のどか氏より「北海道にいまはアイヌ民族がいないと読めてしまう書き方をしてしまっている」というご指摘がありました。本指摘を受けて、「アイヌの人々のいた北海道への日本の入植」としていたテキストを「アイヌの人々の住む北海道への日本の入植」というものに修正しました。元の表現は、日本による入植時点という過去に時制を合わせるため過去形を用いており、アイヌ民族が現在の北海道にはいないということを意味するものではありません。しかし、いまの日本社会に蔓延る「アイヌ民族否定論」を肯定する表現としてとらえられることは本意ではないため、より厳密なかたちに当該表現を修正しました。





